趣味や実用のために3Dプリンターを始めてみたい!でもいきなり高いのを買って失敗したら…
とお考えなら1万円台で買える3Dプリンターはいかがでしょうか?
驚くべきことに、3Dプリンターの低価格化が進み、今や1万円台で3Dプリンターが買えてしまうんです。
そんなに安くてちゃんと動くの?と思うかもしれませんが、たしかに値段の高い機種と比べると、機能は若干劣る部分もあります。
でも造形自体は問題なく可能です。
1万円台で買える3Dプリンターの特徴や、具体的な商品の紹介をしたいと思います。
この記事の目次
1万円台で買える3Dプリンターの特徴
具体的な機種の紹介の前に、1万円台で買える3Dプリンターの特徴をまとめてみました。
造形方式は「熱溶解積層方式(FDM)」
3Dプリンターの造形方式は多々ありますが、家庭用として現在普及しているのは下記の2種類。
- 熱溶解積層方式 (FDM)
- 光造形方式 (DLP)
ですが、1万円台で購入できる3Dプリンターとしては、熱溶解積層方式 (FDM)一択となります。
紐状の「フィラメント」と呼ばれるプラスチック材料を熱で溶かして所定の形状に積んでいくイメージです。
光造形方式 (DLP)は高精細なディティールを再現できますが、FDMは仕上がりの見た目という点では少し劣ります。
でもそこそこ強度の高い部品を作ることが出来るので、幅広く応用可能です。
簡単な組み立て式
1万円台の3Dプリンターは簡単な組み立て式が多いです。
組み立て式と行っても、パーツをネジ数本で固定すれば完了するような簡単なものなので心配無用です。
全軸シャフトガイド、ベルトドライブ
FDM形式の3DプリンターはノズルやベッドがX, Y, Z各軸方向に動きます。
その各軸が稼働するためのガイドの種類がいくつかあります。
高級な機種ではリニアガイド、少し安価な機種だとアルミプロファイル(アルミフレーム)トローラーを使ったもの、さらに安価な機種ではシャフトを使ったガイドとなっています。
1万円で買える3Dプリンターは全軸がシャフトガイドです。
シャフトガイドのメリットは安価に作れる点ですが、デメリットとしては剛性が低く変形しやすい点。
造形物の仕上がりや精度が低くなる可能性がありますが、1万円台の3Dプリンターはサイズが小さいため、シャフトガイドでもそれほど問題にはならないでしょう。
各軸を駆動する形式としてはボールねじや台形ねじ、ベルトなどがありますが、1万円台では「ベルトドライブ」となります。
ネジを使った方式よりは精度が出にくいですが、必要十分といえます。
少しだけ高級な機種だとX, Y軸はベルト、縦方向のZ軸は台形ねじ、という組み合わせが多いです。
Z軸がベルトだと、ノズルの重さによるベルトの伸びにより精度に影響が出る可能性がありますが、1万円台の3Dプリンターはノズル周辺の構造物(X軸等)もコンパクトゆえ軽いため、そこまで問題にならないでしょう。
ガイド方式、駆動方式ともにサイズに対して合理的な選択をしていると言えます。
フレーム形式は片持ち式
Z軸(高さ方向の軸)の動きによりX軸(左右方向の軸)ごと上に上がっていきますが、1万円台の3DプリンターではX軸が片持ち式となっている機種が多いようです。
片持ち式のメリットはコンパクトで安価に作れることですが、両持ち式と比べると、剛性の面ではどうしても劣ります。
1万円台の3Dプリンターは造形サイズが小さいのでそこまで問題はないと思いますが。
1万円台でも、両持ち式の3Dプリンターもあります。
ヒートベッドがない (PLA専用)
1万円台だと、ヒートベッドがない機種が多いです。
ヒートベッドとは、造形物をプリントする土台をヒーターで温める機能のこと。
冷たいベッドに溶けた樹脂を積層すると、温度変化で樹脂が急激に収縮し、ベッドから剥がれてプリント失敗となる可能性が高くなります。
特にABS樹脂は収縮が大きいため、ヒートベッドは必須と考えたほうが良いでしょう。
PLAだとヒートベッドなしでもそこそこいけるので、ヒートベッドがない3DプリンターはPLA専用と考えましょう。
LCD(液晶表示器)もない
1万円台だと、3Dプリンター本体にLCD(液晶表示器)がないものが多いです。
液晶表示器で何をするかというと、プリヒート(予熱)の操作をしたり、プリントするGcodeファイルを選んだり、プリントスタートを指示したり、造形残り時間の確認ができたりします。
LCDのついていない3Dプリンターだと、ボタンが4つくらいついていて、ホームポジションに移動やプリントスタート、ストップなどを操作します。
SDカード内に複数保存したGcodeファイルを選ぶことができないので、最後に保存したファイルがプリントされる、と言った動作になるようです。
プリント自体の設定(温度や各軸の動作)はGcodeファイルに記述されているので、LCDがなくてもプリント自体には大きな支障はないとは言え、ちょっと不便かもしれません。
micro SDカードでgcodeファイルを入れる
3Dプリンターにはmicro SDカードでgcodeファイルを受け渡す機種がほとんどです。
LAN経由でデータを送ったり、PCと直接USBで接続してデータを送ることはできないようです。
microSDカードにGcodeファイルを入れれば良いので、PCのそばに3Dプリンターを置く必要がない、というのはある意味メリットかもしれません。
造形サイズが小さい
1万円台の3Dプリンターの造形サイズは大きくても12cm四方となっています。
めいいっぱいにプリントして、手のひらに乗るくらいのサイズでしょうか。
2~3万円出せば、20cm四方を超えるサイズがプリントできる機種がいくつもあるので、小さい造形サイズで問題ないかを確認しておきましょう。
エンクロージャーのないオープン型
エンクロージャーと言うのは外装の箱のことですが、1万円台で買える3Dプリンターは箱のないオープン型が多いです。
エンクロージャーがあると、プリント時の温度が安定して、造形物のし上がりが良くなったりします。
なくても、そんなに困ることはありませんが、可動部に迂闊に触れてしまうと怪我をするかも。
どこのメーカーなのかよく分からない
Amazonで売られている格安3Dプリンターは、ブランド名の記載がありますが、メーカーがどこなのかよく分かりません。
というのも、同じ形の3Dプリンターが複数のブランドで売られているからです。
どれも中国製と言うのはほぼ間違いないですが、どこで作っているんでしょうね?
1万円台で買える3Dプリンターのメリット
1万円台で買える3Dプリンターのメリットは主に次の2つでしょうか。
- とにかく安い
- コンパクト
とにかくお金をかけずに、3Dプリンターを体験してみたい、という人がターゲットとなりそうです。
色々改造したりして、じっくり3Dプリンターを学びたい、という人にはあまり向いてないかもしれません。
造形サイズが小さいがゆえの、3Dプリンター本体のサイズが小さいことも、設置場所が限られている場合にはメリットとなります。
1万円台で買える3Dプリンターのデメリット
続いては、1万円台の3Dプリンターのデメリット。
LCDがないのでプリントするファイルを選べない
プリントしたいファイルが複数ある場合、LCD(液晶表示器)でファイルを選んでプリントすることがないので、ちょっと不便ですね。
違うファイルをプリントするたびに、microSDカードをPCに挿入してファイルを書き込まなければいけません。
ヒートベッドがないので使える素材が限られる
ヒートベッドがないのでPLAくらいしかプリントできません。
3Dプリントに慣れてきて、ABS等の違う樹脂にも挑戦したい場合に難しくなります。
造形サイズが小さい
コンパクトなのはメリットですが、その裏返しに造形サイズが小さいのはデメリットと言えるでしょう。
購入前にプリントしたいものが決まっている場合は、造形可能なサイズをよく確認しましょう。
1万円台の3Dプリンターは初心者向けじゃない?
値段が安い = 初心者向けのイメージがありますが、1万円台の3Dプリンターの場合はどうでしょうか?
確かに、はじめて3Dプリンターに触る初心者を意識した商品設計となっていますが、本当に簡単に扱えるかどうかは疑問があります。
特に、ヒートベッドを搭載していない機種が多いので、プリント中に造形物が剥がれる危険性が少し高くなります。
本当に初心者向けの3Dプリンターが必要なら、2万円台後半になりますが例えば、「ダヴィンチ nano」などがあります。
完成品で、ベッドの高さのキャリブレーションも自動、純正フィラメントをセットすれば温度などのパラメーターも自動でセットされます。
1万円台で買える3Dプリンター紹介
では、実際に購入できる1万円以下の3Dプリンターを見ていきましょう。
価格はその時によって変動しますので、もしかしたら1万円台じゃなくなってるかも。
あくまで記事執筆時点では1万円台だったということで。
オレンジ外装の片持型 S SMAUTOP (1万円台前半)
オレンジ色の外装が映える、オープンフレームの片持型3Dプリンターです。
1万円台の3Dプリンターを探すと、やたらとオレンジの商品が目に付きます。
少々安っぽい感じがしますが、実際安いんだから問題ありません。
| 造形サイズ | 100 × 100 × 100 mm |
|---|---|
| フレーム構造 | 片持ち |
| ヒートベッド | なし |
| ガイド形式 | 全軸シャフト |
| 駆動形式 | 全軸ベルト |
| エンクロージャー | オープン |
| LCD(液晶表示器) | なし |
1万円台では珍しい両持ち型フレーム S SMAUTOP (1万円台半ば)
フレームが門型、つまりX軸を両持ちで支えるフレーム構造となっています。
Z軸を含む全軸がベルト駆動ですが、Z軸(縦方向の軸)左右2本それぞれにステッピングモーター、ベルトがついている、謎の豪華仕様となっています。
左右両方をベルトで駆動させることで、X軸の傾きが少なくなり、より精度の高い造形が可能となっています。
| 造形サイズ | 100 × 100 × 100 mm |
|---|---|
| フレーム構造 | 両持ち |
| ヒートベッド | なし |
| ガイド形式 | 全軸シャフト |
| 駆動形式 | 全軸ベルト |
| エンクロージャー | オープン |
| LCD(液晶表示器) | なし |
ヒートベッド搭載、水色の外装の両持ち型 SUKIDA (1万円台後半)
色が違うがSMAUTOPのと同じものと思われます。
ただし、1万円台の3Dプリンターにしては珍しくヒートベッドを搭載しているのが最大の特徴です。
ヒートベッドにより造形の安定性が増します。
外装が水色なのが、オレンジよりも良い感じと思いますが、それぞれ好みの問題ですね。
| 造形サイズ | 100 × 100 × 100 mm |
|---|---|
| フレーム構造 | 両持ち |
| ヒートベッド | あり |
| ガイド形式 | 全軸シャフト |
| 駆動形式 | 全軸ベルト |
| エンクロージャー | オープン |
| LCD(液晶表示器) | なし |
1万円台では珍しいクローズタイプの筐体を採用 Aning (1万円台後半)
1万円台としては珍しく、ボックス型でクローズタイプのエンクロージャー(筐体)を採用しています。
冷たい風が吹き込んだりすると、急激な温度変化で造形が失敗することがありますが、クローズタイプの筐体を備えているので、多少なりともそのような失敗を防ぐことができます。
表示機としてOLEDを備えていて、造形ファイルの選択や造形時間の確認なども行える点もポイントが高いですね。
ただし、ボックス型のエンクロージャーを備えている分、造形サイズは他の機種より少し小さく80mm 四方となっています。
| 造形サイズ | 80 × 80 × 80 mm |
|---|---|
| フレーム構造 | 方持ち |
| ヒートベッド | なし |
| ガイド形式 | 全軸シャフト |
| 駆動形式 | 全軸ベルト |
| エンクロージャー | クローズ |
| LCD(液晶表示器) | あり (正確にはOLED) |
Yitre (1万円台半ば)
オレンジ外装の片持型 S SMAUTOPと似たスペックの片持型で
土台部分(Y軸周り)がほぼシャフトで構成されていて、じゃっかん華奢な印象を受けます。
全軸ベルト駆動、シャフトガイド
コントロール基板が本体と分離していてケーブルで繋がっています。
小さいですがLCD(液晶表示器)っぽいものと操作用ツマミらしきものが見えますが、詳細不明です。
ELET, PORIというブランドでも同型が売られています。
| 造形サイズ | 100 × 100 × 100 mm |
|---|---|
| フレーム構造 | 片持ち |
| ヒートベッド | なし |
| ガイド形式 | 全軸シャフト |
| 駆動形式 | 全軸ベルト |
| エンクロージャー | オープン |
| LCD(液晶表示器) | あり? |
EasyThreed (1万円台後半)
Yitreとほぼ同じに見えますが、よく見ると操作部が異なります。
こちらは4つのボタンで操作するタイプのようです。
それ以外のスペック的には同じと思われます。
| 造形サイズ | 100 × 100 × 100 mm |
|---|---|
| フレーム構造 | 片持ち |
| ヒートベッド | なし |
| ガイド形式 | 全軸シャフト |
| 駆動形式 | 全軸ベルト |
| エンクロージャー | オープン |
| LCD(液晶表示器) | なし |
1万円台で買える3Dプリンターのまとめ
いくつかの機種を紹介しましたが、それほど大きな違いはない感じです。
試しに3Dプリンターを買ってみたい、というのであれば、どれを選んでもOKです。






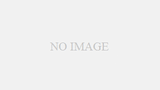
コメント